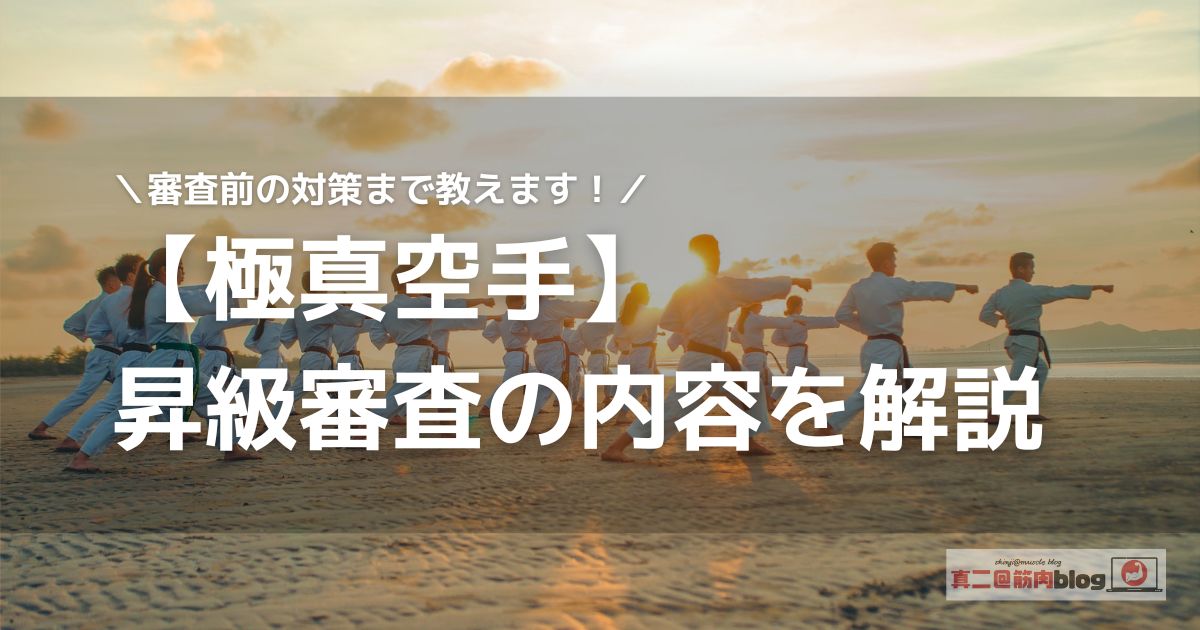
極真空手において、昇級審査は次のステップにいく大きな節目。
しかし、審査の内容が分からず大きな不安を抱えている方も少なくありません。
特に入門して間もない方や初級の帯の方だと、落ち着かずに前日の夜も眠れないでしょう…
こんな疑問にお答えします
- 昇級審査の内容がわからない
- 昇級審査で合格するためのコツが知りたい
- 昇級審査に向けた対策が知りたい
記事の信頼性
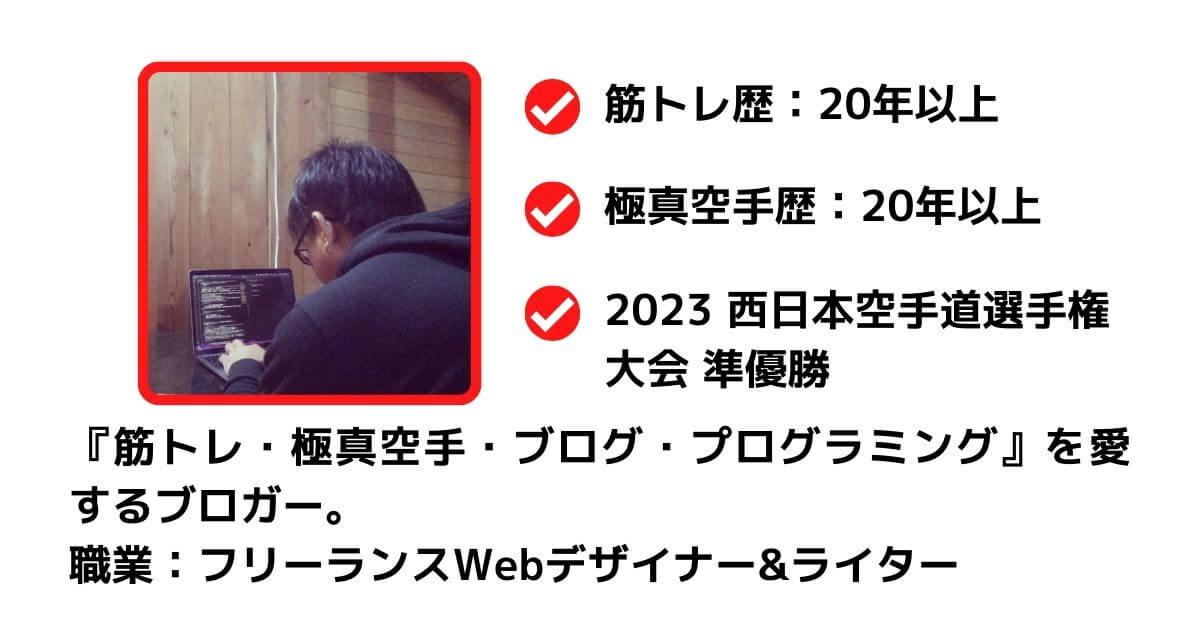
この記事を書いている僕は、極真空手歴・筋トレ歴ともに20年以上。
15歳で極真会館に入門し、現在も日々稽古に打ち込んでいる現役の空手家です。

しかし、しっかりと内容を把握して事前に対策しておけば、当日の不安を和らげることができるでしょう。
そこで今回の記事では、極真空手の昇級審査の内容や対策について詳しく解説していきます!
自信をつけて審査に挑めるよう、ぜひこの記事を参考にしてみてください!

極真空手の昇級審査の内容
まずは、昇級審査の内容の全体像を見ていきましょう。
事前に把握しておくことで、より安心して昇級審査に挑めます!
1-1 基本稽古の確認
はじめに行われるのは基本稽古の確認。
ここでは、道場で普段やっている基本的なことが審査されます。
主に見られる項目
- 基本稽古
- 体の柔軟性
- 基礎体力
- 二段蹴り(緑帯以上は飛び後ろ廻し蹴り)
普段の稽古をマジメに取り組んでいる方なら、基本稽古の審査でコケることはまずないでしょう。
次に体の柔軟性については、初級者であれば努力義務で多めに見てもらえる場合もあります。
しかし、上級者となると股割りをして胸が床につくことが必須。
常日頃からしっかりと柔軟運動をやっておきましょう。
また、基礎体力の審査では拳立て伏せとジャンピングスクワットが各50回ずつ。
さらに、椅子に乗って構えているミットを二段蹴りで当てなければなりません。

1-2 型審査(それぞれの級位に応じて)
型審査ではそれぞれの級位で指定された型を行います。
各級位で行う型は以下のとおり。(どの型を行うかは支部により若干異なる場合があります)
| 帯の色 | 段位・級位 | 審査で行う型 |
|---|---|---|
| 白帯 | 無級 | 太極1・太極2・足技太極1 |
| オレンジ帯 | 10級・9級 | 太極3・足技太極2・足技太極3 |
| 青帯 | 8級・7級 | 平安1・平安2・三戦 |
| 黃帯 | 6級・5級 | 平安3・平安4・安三 |
| 緑帯 | 4級・3級 | 平安5・撃砕大・突きの型 |
| 茶帯 | 2級 | 最破・撃砕小・転掌 |
| 茶帯 | 1級 | 平安1、2、3、4、5裏・十八・鉄騎1 |
| 黒帯 | 初段 | 征遠鎮・臥龍・鉄騎2 |
※茶帯1級からは昇段審査
上記のとおり、たくさんの型を覚えなければなりません。
実際の審査では細かくチェックされるので、動きの細部まで習得しておきましょう!

1-3 組手審査
最後に行われるのが組手審査。
サポーターやヘッドギアを付けて実際に試合形式で行われます。
試合形式といっても相手を倒すことだけが目的ではなく、しっかりと組手ができているか?がもっとも重視されるポイント。
ただガムシャラにつっこむのではなく、相手の攻撃をさばいて自分の技を返せることが大切です。
とはいえ、初級者の場合だと緊張してしまい、勢いだけでつっこんでいく方も少なくありません。

昇級審査で合格するためのコツ
結論からいうと、昇級審査で合格するためには普段から真剣に稽古に取り組む!これに尽きるでしょう。
そもそも、昇級審査を受けられるということは、道場の責任者が承認した証。
次の級に昇級できる実力がなければ、受審資格を得ることはありえません。
もちろん、ただ一生懸命やるだけではなく、既定の型や組手も上達する必要があるでしょう。
そのためにも、常日頃の稽古に対する姿勢が重要となるんです。
あなたが昇級審査を受けられるのは責任者に認めてもらえたということ。
自信を持って審査に挑みましょう!

昇級審査に向けた対策
誰もが万全の対策をして昇級審査に挑みたいと感じているハズ…
そこでここからは、審査に向けた対策について解説していきます。
3−1 稽古を休まない
まずは、当然ですが普段から稽古に参加することです。
稽古を休めば休んだだけ不安が大きくなるでしょう。
そもそも、普段の稽古で自信をつけていなければ、落ち着いて審査を受けることはできません。
不安を払拭するためにも、まずは稽古に休まず参加しておきましょう!

3−2 型の三要素を意識
極真空手の型に限った話ではありませんが、ただ順番や形を覚えるだけではまったく意味がありません。
そこで、極真空手の「型の三要素」と呼ばれる技術を意識しておきましょう。
型の三要素
- 技の緩急
一定の速さで動作をするのではなく、すばやい動作、ゆっくりな動作を使い分け、メリハリをつけましょう。 - 力の強弱
ただ力強く突きや蹴りをすれば良いわけではありません。例えば、当たる瞬間に力を入れるなど強弱をつけるのが良い例ですね。 - 呼吸の調整
攻撃をするときや受けるときなど、力を発揮するときに息を吐くのがポイント。型だけではなく組手でも必要な技術です。

3−3 スパーリングで組手対策
冒頭でもお伝えしましたが、組手審査ではただ相手を倒すことが目的ではなく、いかにしっかりと闘えるかが重要なポイント。
そのためには、普段のスパーリングで正確に受け返しができるようにしておくことが重要になります。
もちろん、ただスパーリングをたくさんするだけではダメ。
常に高い意識をもって取り組むことで、上手な組手ができるようになります。
さまざまなパターンの突きや蹴りに対して、正確にさばいてすばやく技を返せるように反復しておきましょう!

まとめ
いかがだったでしょうか?
今回の記事では、極真空手の昇級審査の内容や対策について詳しく解説しました。
そもそも昇級審査は何度経験していても多少は緊張するもの…
まずは常日頃から普段から稽古に休まず参加し、高い意識を持って取り組むことで不安を和らげられます。
また、審査前の対策としては型の三要素を意識し、スパーリングで実践慣れしておくことも大切でしょう。
この記事で学んだことを参考にして、自信を持って昇級審査に挑んでください!

【関連記事】極真空手の昇段審査について知りたい方は、こちらの記事も合わせて読んでみてください! 格闘技の中でも特にストイックなイメージのある極真空手。その頂点に君臨する黒帯はまさに憧れの存在ですよね。いったい、極真空手の黒帯とはどれくらいすごいのでしょうか?・極真空手の黒帯のすごさが知りたい・黒帯取得までの具体的な期間を知りたい・昇段審査を受けるための条件や難易度が知りたい

極真空手黒帯はどれくらいすごい?取得までにかかる年数や条件は?
